全てはここから始まった。
どーも、たけGです。
シリーズの記念すべき第1作「ゴジラ」
公開時は1954年。
僕が生まれるよりも、ずっと前に公開された映画なんですよね。
って言うか、よくよく計算してみると、僕の父親が中高生の頃に公開された映画なんですよ。
そう気付いた時に父親に「ゴジラ」を興味を持ったことはなかったのか聞いてみたのですが、特に興味は持たなかったとのこと。
今と違って映画を観に行くのも容易ではなかった時代だったので、わざわざ映画館に足を運んでまで観に行くことはなかったそうで。
映画館へ比較的行きやすくなってきた頃には、「ゴジラ」は子供が見るものといったイメージを持っていたそうです。
と、そんな脱線話はさておいて初代「ゴジラ」
父と母がまだ結婚どころか出会って付き合ってもないんじゃないかって頃の、そんな昔の作品なわけですよ。
(そこまでは突っ込んで聞いてませんが)
記憶が正しければ84年版の「ゴジラ」を見たよりも更にあとでしたね。
「vs.ビオランテ」よりも後だったかもしれない。
それだけ我が家にビデオデッキが導入されるのが遅かったわけなんですけども、それまでの僕の中での初代「ゴジラ」は、ムック本の情報やノベライズされていた小説版が全てだったんですよね。
なのにこの初代「ゴジラ」をいうものを勝手に神格化していた節があったんですよね。
84年版「ゴジラ」で初めて映画館でゴジラ映画を見てゴジラ好きを公言しはじめ、テレビで放映された過去シリーズを欠かさずチェックするようになり、見ていない映画の内容は本で知るのがほとんどでした。
そこで他のゴジラ好きな友人達と話すと、必ず出てくるのが「初代は別格」。
それは当時の雑誌の情報などでも大体がそのようなスタンスで書かれていました。
なので、映画を一切観たことがなかった僕も、「初代が最高だよねやっぱり」とか話していたんですよ。
テレビで見たことがある「モスラ対ゴジラ」とか、「三大怪獣地球最大の決戦」とかが大好きだったくせに。
一方で、白黒映画で自分が生まれるよりもずっと前の映画なんだから、それだけで名作補正のフィルターがかかっているに決まってるだろうし、最新のゴジラを見た後では絶対に見れたもんじゃない古くさい映画なんだろうなぁとか失礼なことを思ったりもしていたわけなんですよ。
ですが、ある日我が家にもビデオデッキが導入されてレンタルビデオ店なるものに初めて行った時に、一度はやっぱり見ておこうかなと思って借りてみたんですよ。
見るまでは昔の映画だとナメた部分があったと思うのですが、それが初めて鑑賞して世間の評価が正しかったことを痛感したんですよねぇ。
それまで見てきたゴジラ映画、それも映画館で観た84年版の「ゴジラ」でも感じたことのなかった恐怖と絶望感を感じたんです。
ゴジラという未知の存在に対する恐怖、ゴジラの猛威に対し為すすべがない人たちの絶望感、ゴジラによって家族や住居を失った人たちのやり場のない悲しみや怒りを、白黒の映像を通じて強く感じることが出来たんですね。
登場人物たちに関してもそうでした。
人間ドラマにおける台詞回しや人物像に古さを感じるのは仕方がないとしても、十分に鑑賞に耐えうるものでした。
オキシジェン・デストロイヤーを発明した芹沢博士についてもそうです。
ムック本などでの情報しか初代「ゴジラ」のことを知らなかった当時の僕は、芹沢博士のことを単なるマッド・サイエンティストだと勝手に思い込んでいた節がありました。
ですが、初めて見た映画の中の芹沢博士は至極まっとうな人間であり、それも人間として非常に強い一面と、非常に弱い一面を合わせ持つ人物でした。
同時に自分の発明したものに対する責任感を常に抱き、強い意志も持っている人でもありました。
その芹沢博士の弱さと強さを知っていて、感動したからこそ、後の「ゴジラ・ジェネレーションズ」というゲームで、芹沢博士を巨大化するという悪ノリを通り越した暴挙を行っているのを知った時に、なにワケわかんねぇことやらかしてんだと憤り、今の今まで購入して遊ぼうという気持ちになれなかったものなのですが。
恐らくは今後も遊ぶことはないゲームの話はさておいて、そんな思い出のある初代「ゴジラ」。
DVDでは見た記憶がないな…。
故に、アマプラで久しぶりに見た時にはまたもや自分の中で思い出名作補正がかかっているんじゃないかと思っていたのですが、いやいやどうしてどうして。
何年経っても、何回見直しても、白黒なのに今見ても十分楽しめる作品でした。
やっぱりゴジラが怖い。
水爆が生んだ大怪獣ゴジラ。
最新作「シン・ゴジラ」まで見てきて、久々に見た初代「ゴジラ」でしたが、この初代から感じる恐怖や絶望感はシリーズ随一だと今も断言できます。
この点に関しては、2019年現在においても、どのシリーズ作品においても初代を超えていない、というか再現できていないと思います。
例えば、それこそ直近の作品である「シン・ゴジラ」
ゴジラを未知の存在として描いているのは初代の後は「シン・ゴジラ」のみなのですが、捉え方は両者にはかなり違いがあります。
初代が描いているのは、ゴジラという未知の存在への恐怖であり、畏怖。
対して「シン・ゴジラ」が描いているのは、ゴジラという未知の存在の脅威に対し、現代日本はどう対応出来るかというもの。
初代「ゴジラ」のゴジラは「シン・ゴジラ」に対し、まだ生物的ではありますが、人々の視点は人間には抗えない神のような存在であり、故に恐怖する。
言わば寓話の中の存在であり、故にオキシジェン・デストロイヤーという架空の兵器で持って解決するファンタジー映画なのです。
ですが「シン・ゴジラ」のゴジラは無機質でまさに超生物的な存在ですが、人々はそれに対し抗い、持てるもので解決を試みる。
もし現実世界に大怪獣が現れたら、という存在であり、実在する兵器や技術力を持って解決しようとするシミュレーション的な映画であるとも言えます。
ゴジラに対して逃げ惑う人々や蹂躙される都市は出てきますが、そこにあるのは政府側の人々による日本を守り、ゴジラを滅しようとする強い意思。
ゴジラに対し為すすべない一般人目線でも描かれていた初代と比べると、どうしても恐怖の大きさや人々の絶望感や悲壮感において一歩譲ってしまうなぁと改めて感じたものです。
今回は初代「ゴジラ」について綴ってみました。
さすがに昔の作品ですからね、白黒映画だからと割り切ってみても特撮映像に拙さを感じることは多いですし、登場人物たちの人物像や話し口調に時代を感じることは多いです。
ですが、シリーズの原点にして、今も色褪せないゴジラという未知の存在の恐怖を描いた至高の作品。
「シン・ゴジラ」やハリウッド版最新作「キング・オブ・モンスター」を見てゴジラを好きになったけど、昔の作品だからと見たことがない人がいたら、一度見ておいてほしいと心から思う作品です。
今回はこの辺で。
いつかまたここで会いましょう。


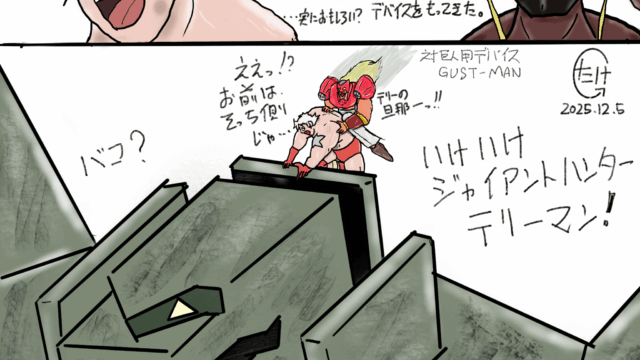
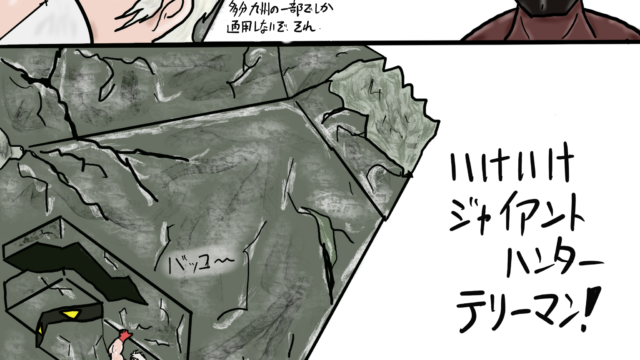
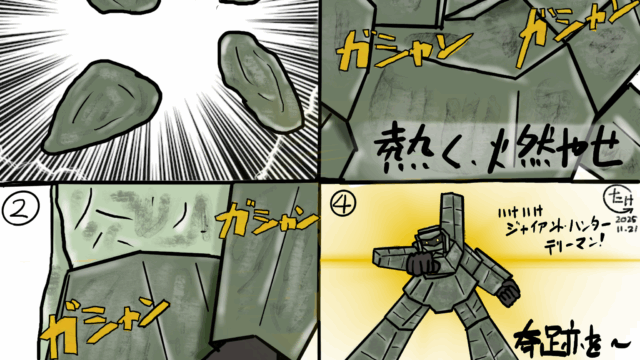



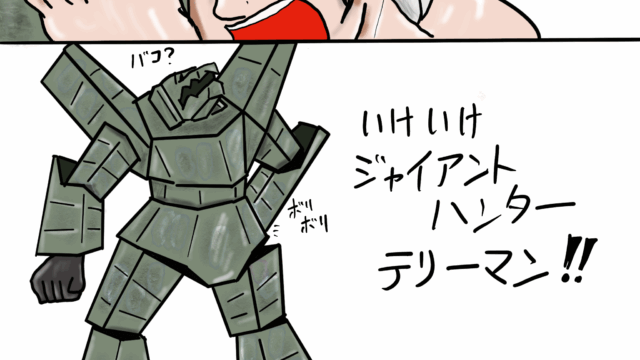






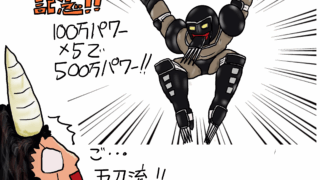
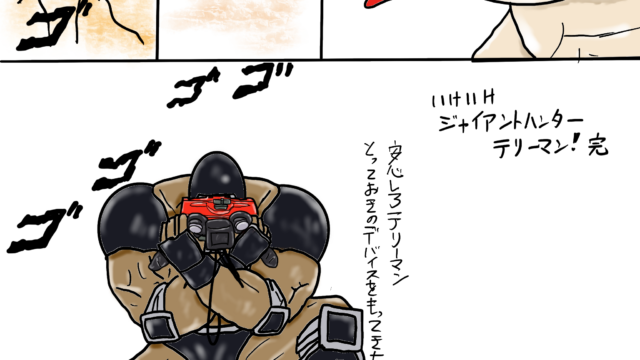
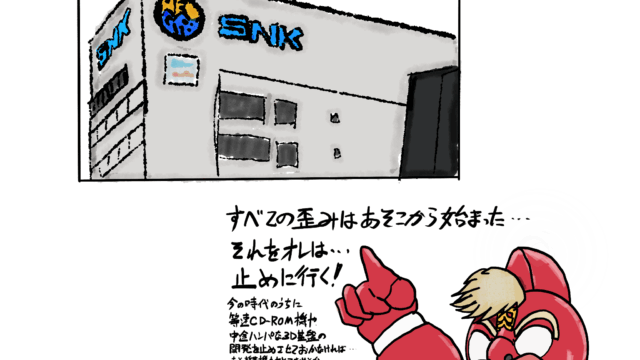




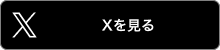



コメント
お久しぶりです。私も先日、大学の図書室で観ました。
もう70年も前の作品とは思えないほど、クオリティの高いジオラマに驚かされました。
白黒の効果もあるかもしれませんが、それでも素晴らしい出来栄えでした。
縦横無尽に動き回り、熱戦を吐くゴジラには、怒りと悲しみの感情を抱きました。
>僕が生まれるよりも、ずっと前に公開された映画なんですよね。
って言うか、よくよく計算してみると、僕の父親が中高生の頃に公開された映画なんですよ。
70年も前というと、先月亡くなった祖父がまだ5歳の頃ですね。祖父もゴジラが好きで、
レンタルビデオの「ビオランテ」を持って行ったらとても喜んでくれました。
>ムック本などでの情報しか初代「ゴジラ」のことを知らなかった当時の僕は、芹沢博士のことを単なるマッド・サイエンティストだと思っていた節がありました。
私もそうでした。ゴジラは被害者の一面を持っている怪物で、彼を倒すためにとんでもない爆弾を作り葬った、人類の味方ではあるけど、いい人と言い切れないそんな存在のように思っていました。
けれども蓋を開けて観れば、正義感の強い人で、自分の発明を悪用されてしまうのを、何よりも恐れる素晴らしい人でした。設計図を燃やし、自身もろとも爆弾の犠牲となってその存在を抹消する。彼は立派な科学者でした。
爆弾の製造にも、使用を渋る理由にも、ゴジラが一切関係していないのが良かったのだと思います。だからこそ、ゴジラの被害に遭い苦しむ人達や、破壊された街、真摯に平和を願う少女の歌声、を見ての彼の決断に、なんの違和感も感じなかった。
爆弾が起動し、もがき苦しむゴジラが、一度浮上して雄叫びを上げたのが、とても印象深かったです。
しっかし本当の悲劇は、この爆弾によってデストロイアと機龍という二大悪夢が、後のゴジラを襲ったことではないでしょうか。人間の考えることは、本当に恐ろしい。
時代を感じる台詞や、チープさを感じる場面もありましたが、無駄のなくすっきりとした名作です。
個人的には「シンゴジラ」よりも、好きです。
>縦横無尽に動き回り、熱戦を吐くゴジラには、怒りと悲しみの感情を抱きました。
抱きました。ではなく、感じましたです。誤字失礼しました。
>マルゲリータさん
熱いコメント、ありがとうございます!
70年以上前の白黒映画で今となってはチープさが否めない本作ですが、これが最先端の映像だった当時はものすごい迫力で、そして怖くて悲しい作品なのではないでしょうか。
そんな感情が湧き上がる作品は以降のシリーズで、どんなに映像表現が増しても今作以上のものはないと思います。
「シン・ゴジラ」も素晴らしい作品ではありましたが、やはり「ゴジラ」があってこその作品。
未知のものに対する恐怖や、脅威に立ち向かう人々の葛藤を描いていても、初代「ゴジラ」の描いた悲しみのようなものは感じられないと思います。
その後のデストロイアや機龍にも繋がる本作ですが、そう思うと芹沢博士が危惧していたのはもっともで、命をかけてそれを封印しようとしたにも関わらず、人は過ちを繰り返すのだなあと、改めて思いました。
今の技術でリメイクされたとしても、この雰囲気は出せないのではないかと思うのです。