本日7月19日は、SFC「ファイナルファンタジーⅣ」発売日!
あれからもう34年にもなるのですか…
そんなFF4の思い出を綴っていきたいと思います。
どーも、たけGです。
これは驚いた!
というゲームが誰にもあるのではないでしょうか。
ファミコンにしろプレステにしろSwitchにしろ、生まれて初めて遊んだゲームには誰もが驚いたことでしょう。
また、ハードが進化するごとにグラフィックが向上し、様々な表現方法で魅せられる度に驚かされることも多かったですね。
僕もこれまでいろんなゲームで驚かされてきました。
「ドラゴンクエスト」で映画のようなスタッフロールを見た時。
「バーチャファイター」が普通に家で遊べた時。
「ファイナルファンタジーⅦ」がPSで発売された時。
「スーパーマリオ64」で初めてのアナログスティックを操作してピーチ城周りをぐるぐる走り回った時。
「ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド」でどこまでも続くかのような世界を目にした時。
あ、あと「バイオハザード」でケルベロスが窓から飛び込んできた時は思わず声を上げてしまうぐらい驚きましたっけ。
思えばいつの時代もゲームでは驚きの連続でした。
そんな、これまで遊んできたゲームの中で
「これは驚いた!」
と思ったソフトを上げるとすると、僕はまず、SFCで遊んだ「ファイナルファンタジーⅣ」を選びます。

思えば「ファイナルファンタジー」というゲームは、驚きの連続でした。
初作「FF」での横画面の戦闘、アニメーションするキャラクターたち。
いきなり不可避の全滅からスタートする「Ⅱ」
飛空艇で大地を飛び出したらそこは大海原で、全てだと思っていた大地が世界のほんの一部だったということを知らされた「Ⅲ」
ファミコンというハードの限られた制約の中で、FFの表現力にはいつも驚かされたものです。
そしていよいよ新世代のハード、スーパーファミコンで発売されることになった「ファイナルファンタジーⅣ」
余談ではありますが、実はこの「ファイナルファンタジーⅣ」というタイトルが正式に決まるまでの経緯には、ちょっと複雑なものがあるんですよ。
今回のお題である「ファイナルファンタジーⅣ」というゲームは、当初は「ファイナルファンタジーⅤ」として計画されていたものだったという逸話があるのです。
それでは本来の「FFⅣ」はどうなっていたのかというと、当初はファミコンで発売される予定でした。
なにぶん手元に資料もなく、昔のことなのでちょっと記憶が間違ってるかもしれませんが本来の「FFⅣ」と「FFV」の発売について当初は、なんだか首を傾げたくなるような計画で発表されていたように覚えています。
その当時、「Ⅳ」と「Ⅴ」は、ほぼ同じタイミングで発表されました。
「Ⅳ」はFCで、「Ⅴ」はSFCで発売との発表。
ここまではまあ普通、順当ですね。
普通の流れです。
ファミコンで「Ⅳ」を発売し、その後でSFCで「V」を発売する。
まあそれが普通だと思いますよね。
ところが、その時に発表されていた内容は僕の記憶が正しければ、
先にSFCで「Ⅴ」を発売して、その後でFCの「Ⅳ」を発売する
といったものだったのですよ。
先にSFCで「Ⅴ」を発売して、その後でFCで「Ⅳ」を発売???
情報誌でその内容を見た時に、期待するのと同時に「?」と首を傾げたような記憶があります。
いやまぁ、僕の記憶が間違ってるかもしれないけれど、そんな顛末があったように覚えているんですよねぇ。
結局、当初予定されていたFC版「FFⅣ」は陽の目を見ることなくお蔵入りとなり、予定されていた「Ⅴ」が「Ⅳ」として繰り上がることで現在の形に落ち着いたというわけで。
いやそれで良かったでしょう。
幻のFC版「FFⅣ」を見たかった気持ちもありますけど。
ちなみに幻のFC版「FFⅣ」ですが、その後発売されたSFC「聖剣伝説2」のベースになったらしい噂があります。
「聖剣2」はゲームの進行に支障をきたすほどのバグがてんこ盛りな以外は神がかった名作だったので、予定通りにFFⅣとして世に出ていてもそれはそれで面白かったんじゃないかな。
余談はこれぐらいにしておいて、そんなSFC版「FFⅤ」改め「FFⅣ」に話を戻しましょう。
ファミコンからスーパーファミコンに代わり、グラフィックが劇的に進化している事は雑誌の事前情報で見ることが出来ていました。
召喚獣タイタンの地割れで、背景の地形が割れているグラフィックには本当に目を奪われました。
ただ、その当時はもうファミコンからスーパーファミコンへと進化して向上したグラフィックについては、既に他のゲームで当たり前にはなってました。
任天堂がいきなり「F-ZERO」で凄まじい映像表現魅せてくれましたし。
RPGでも「ガデュリン」とか出ていましたしね。
「FFⅣ」の緻密なドット絵は確かに同時期のSFCの他のゲームと比べると、一歩も二歩も抜きん出てましたが、「FF」の美麗なグラフィックは当時から美麗なのが当たり前。
僕が驚かされたのは、グラフィックそのものではなかったのです。
(いやまぁ正直言えばそのグラフィックの美麗さにも驚きはしてるのですが)
事前に行きつけのショップに予約して、発売当日に購入。
カセットをスーパーファミコンにセット。
主人公の名前を入力し、(当時はセシルにはしてなかったと思う…)ゲームスタート。
さぁ、どんなオープニングを見せてくれるのか。
いきなりくろきしとの戦闘で全滅しても、もしくはいきなり落とし穴に落ちるところからはじまっても、もう驚かない自信があるぞ。
こちとらFFシリーズのびっくりスタートには免疫出来てるからな!
そうやって開幕した「FFⅣ」
一瞬の暗転から飛び込んできたのは、飛空艇の船団が編隊を組んでいるシーン。
雄々しく鼓動を突き動かすかのような重々しいBGMを背景に、手前から奥へ飛ぶ飛空艇団。
これまでにない立体的な飛行シーンの演出は、スーパーファミコンの拡大縮小機能を活かしたものでした。

このオープニングを最初に見た時には、度肝を抜かれましたねぇ。
一度セーブして終わらせた後で、もう一回見ましたもの。
そして、陳腐な表現にはなってしまいますが、こう思ったものです。
まるで映画みたいだ…
と。
今のPS4やPS5、もしくはSwitchのゲームなどを見慣れた若い方々には鼻で笑われてしまうかもしれませんが、当時はスーパーファミコンこそが最先端のゲーム機。
この16ビットのドット絵で描かれたオープニングの映像は、本当に映画のようだと思えたものなのですよ。
オープニングだけに留まらず、祖国に忠実なる暗黒騎士であることに悩み、葛藤するセシル。
そのセシルと親友カインの友情と、ヒロインのローザを巡る愛憎劇。
大地に現れ、世界を焼き尽くそうとする巨神。

伝承とともに現れる魔導船。
やがては宇宙にまで飛び出して、月の民をも巻き込む物語。
全てが映画のようだと、驚きの連続であったのですよ。
いやマジで。
新世代機スーパーファミコンの機能を最大限に活かしきり、グラフィックの向上だけでなくファミコンのRPGとは違うということを、まざまざと見せつけてくれたわけです。
驚かされたのは物語や演出だけではありません。
システム面でも次世代の驚きを感じさせてくれました。
それが、今作「Ⅳ」より採用された新しい戦闘システムである、アクティブ・タイム・バトル(ATB)。
前作「Ⅲ」までは横画面でキャラがアニメーションするとは言え、基本的にはドラクエと同じコマンド選択式ターン制のオーソドックスな戦闘システムでした。
しかし今作からはターンは敵味方ともに素速い順に1人ずつ回ってきて、リアルタイムでコマンドを選択していくATBになってきました。
このあと「Ⅸ」までこの戦闘システムが「FF」のスタンダードとなり、かつ他のゲームでは見られない「FF」のオリジナルとなったのです。
キャラごとにリアルタイムで行動を選択していくバトルは最初のうちは忙しかったけれど慣れていったら本当に楽しくて、好きな戦闘システムになりました。
コマンド選択中も時間が流れる”アクティブ”と、選択中は時間が止まる”ウェイト”を選択出来るのですが、最初のうちはアクティブで遊んでいました。
しかし生来の焦りやすく、テンパりやすい体質からあたふたするうちに冷静なコマンド選択が出来なくなって、ウェイトに切り替えましたっけ。
今までこそFF以外のコマンド選択式のRPGで ATBの影響を受けていると思しき戦闘システムも珍しくありませんが、最初に遊んだ時には初めて体験するこのシステムにはとても驚き、そして感動したものです。
感動と言えば、感動のドラマが展開するのもFFⅣ。
FFⅡと同様にパーティキャラに明確な個性づけがなされており、幾人ものキャラクターたちが登場するシナリオ重視のゲームでした。
同じくシナリオ重視だったFFⅡでは、フリオニール、マリア、ガイの3人が常に固定で、この3人+最後にパーティに加わるダークナイト・レオンハルトの4人を中心に紡がれる物語といった形でした。
ですが、今作Ⅳでは明確にセシルという1人の主人公を設定されており、セシルを中心としたドラマが展開されるのです。
1人の主人公を据えた物語としても、このⅣが実はシリーズでは初めてだったわけで、ここから以降のシリーズに繋がっていきました。
セシルを巡る物語は、ほつれた糸のようにぐるぐると絡み合っておりまして、どんな星の元に生まれたら、こんなに災難だらけの人生を歩めるのかというようなトラブル続き。
自分の恋人ローザに横恋慕しているのが親友のカイン。
カインはローザへの思いが故に、裏切りに裏切りを重ねます。
おれはしょうきにもどった!
は、カインの忘れられない名(迷)セリフでしたねえ。
そしてもう1人のヒロインとも言うべきリディア。
召喚士リディアの母親を死なせ、故郷の村を焼き払ったのも成り行きとは言えセシル、そしてそのリディアの命を救い守ったのもまたセシル。
リディアからの複雑な愛憎も背負うことになるわけで。
更にはバロン王の命によりクリスタルを強奪したことによって、パロムとポロムをはじめとしたミシディアの人々から恨みを買い、疎まれ、疑心の目を向けられて。
そんな負を積み重ねてきた過去を断ち切るべく試練を乗り越えて、暗黒騎士から聖騎士パラディンへとなるものの、その後に自分達を翻弄し続ける大敵が生き別れの実の兄だと知り、兄弟で戦いあうことになる。
そんなセシルを信じて前に進めるために自らを犠牲にしてその身を投げ出し、散っていく仲間たち。
最初はセシルに疑いを持っていたパロムとポロムが、セシルを信じるに至り彼を守るために自信を石にして絶体絶命の危機を救ったシーンでは泣けたなぁ。
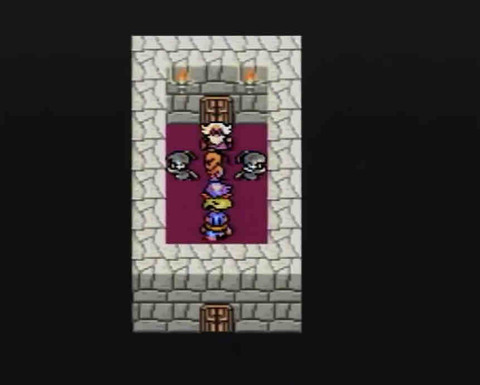
他のシリーズの主人公達も大概な人生を歩んでいるわけですが、波乱っぷりやドロドロっぷりで言えば間違いなくNo.1でしょうセシルくん。
このように怒涛の展開で繰り広げられるFFⅣのドラマにこれまた驚き、かつ感動したものです。
驚きに満ち満ちていたFFⅣ。
ただ、だからと言って欠点がないわけというわけでもなく。
先に書いた、仲間が次々に身を挺して自己犠牲の精神で散っていくのには最初のうちこそ感動するのですが。
ところが前述の泣かされたパロムとポロムをはじめとして、主人公たちのために命を散らせていった仲間たちが、後にみんな生きていたということが判明。
いや、死んで御涙頂戴こそいい話だ!とか言うわけではないですよ。
生きてるか死んでるかで言えばそれは生きている方がいいに決まってます。
ですが、仲間たちが命をかけて運命に立ち向かい、散っていき、悲壮感漂うBGMの中、残された者たちが悲しみにくれる姿を見せられて、見ているこちらももらい泣き。
それも何度も何度も。
それが後になって実は生きてましたーっ!
って。
男塾じゃないんだから。

何度も仲間達に目の前で死なれて、感動を与えられてきたのはなんだったのか。
あの時の涙と感動を返せと言いたい。
一説によると、同様に自己犠牲によって仲間が次から次に死んでいったFFⅡの時に批判が大きかったので、実は死んでなかったんだよー的な展開にしたとも言われてますが。
それならそれで自己犠牲による御涙頂戴パターンを繰り返すな!と言いたい。
この「Ⅳ」の、実は生きてました展開のおかげで、後の「FFⅦ」でエアリスは絶対生きている!生き返るに違いない!と思ってしまったじゃないですかあ!
今回はSFC「ファイナルファンタジーⅣ」の思い出語りでした。
FFシリーズの中での好きな作品なら「Ⅲ」や「Ⅵ」、やり込んだ度合いだったら「Ⅴ」や「Ⅶ」など、他のナンバリングタイトルが上がるかもしれません。
個人的に1番好きなFFは?と聞かれたら、今作「Ⅳ」は多分候補に上がらないんじゃないかな。
あくまで個人的にはですが。
ですが、最初に遊んだ時の印象深さなら、初FFだった「Ⅱ」と同じくらい、この「FFⅣ」が印象深いものでした。
やっぱりファミコンからスーパーファミコンに移ってのはじめてのFFだったというのも大きいでしょう。
ファミコンからスーパーファミコンへの進化でグラフィックなどの表現力の進化があって、それはアクションゲームやシューティングゲームでゲームセンター並みのものが家で遊べるようになる、というのが最初は大きかったものです。
一方で家でしか遊べないゲーム、ファミコンでこそ楽しめていたRPGをSFCの美麗なグラフィックと派手な演出で楽しめるということに衝撃を覚えたと言いますか。
特に、先陣を切って発売された「FFⅣ」の映画のような演出にはホント、ド肝を抜かれたものです。
先陣を切ったというなら「ガデュリン」が先でしたが、こちらは遊んでなかったもので。
その後、PS、PS2とハードが移り変わる度にFFも進化していきました。
当然、映像表現力もどんどん上がっていき、「FFⅦ」のミッドガルや、「FFⅩ」の眠らない街ザナルカンドを初めて見た時は、ホーッと感嘆のため息をついたものです。
美しさで言えばもはや、SFCのそれとは比べるべくもなく。
ですが、最初に目にした時の驚きというか、衝撃の度合いで言えば、「FFⅣ」の赤い翼の編隊が飛行するシーンからはじまるオープニングを越えるものには未だ出会っていないのです。
思い出補正がかかっているかもしれないというのは否定しませんけどね。
今回はこの辺で。
いつかまたここで会いましょう。
いいですとも!

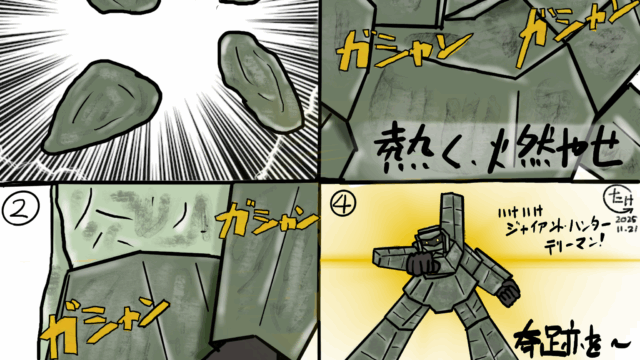
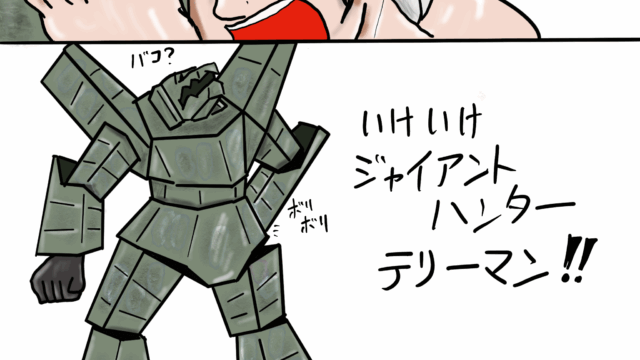




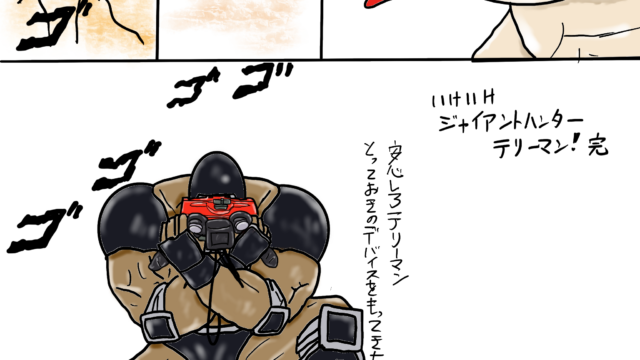





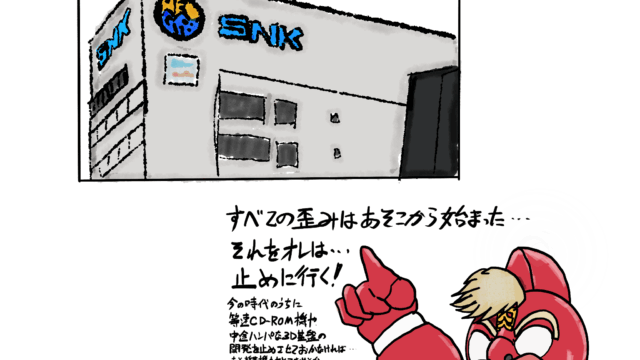

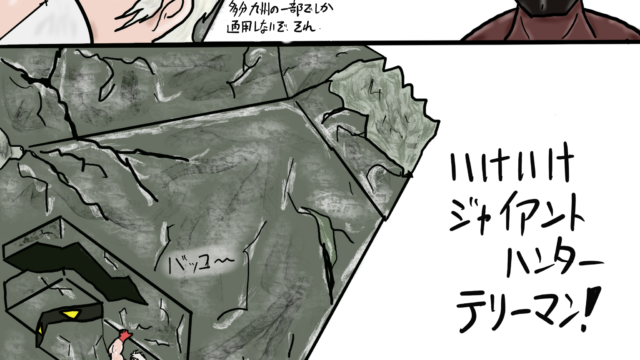
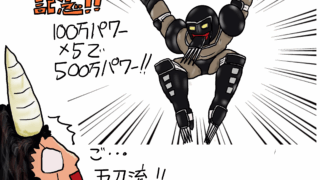

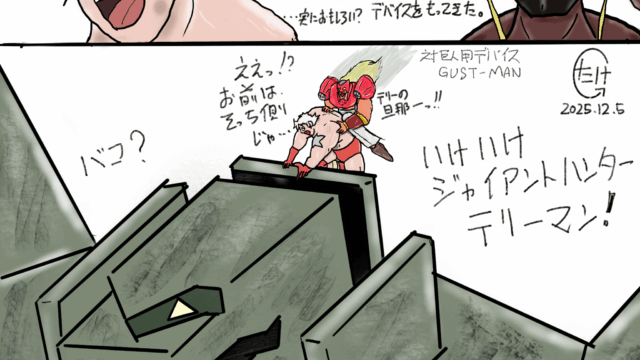



コメント
たけGさんこんばんは。
FF4を初プレイした時に、特に「SFCスゲー」って思ったのが「音楽」ですね。
オーケストラ調の音楽がすごくて、特にバロン城の音楽が感動しました。
因みに、自分を含む友人達はカインの評価(と言うか奴の行動)については大まかに二つに分かれました
1、ローザの事もあるし仕方ないよね…
2、裏切りまくるのもいい加減にしろよな…
呂布かテメーは
自分は2でしたが、大人になってカインの葛藤もあり今は1寄りの気持ちです
>名無さん
こんばんは。
FF4は音楽も確かに衝撃でしたよね。
ファミコンでは不可能だった重厚なサウンドがとにかく驚きでした。
赤い翼の飛行シーンから、その後のバロン城の音楽まで、とても響きましたね。
カインは裏切るたびにまたか!って思ったもんです。
近年DS版やPSP版を遊び直した時には、もはや定番のネタとして楽しめましたが、当時はなんだかイライラさせられたものです^^;
セシルのうじうじした態度にも、イライラさせられてたっけなあ
>>2
セシルの態度には、たけGさんに近い事を言っていた人はいましたね
自分はFF4でハードの進化を感じましたがFF以外でそれを思ったのが、アクトレイザーとテイルズオブファンタジアですね。