令和元年5月1日。
とうとう平成が終わり、令和の時代になっちゃいました。
どーも、たけGです。
平成になった年の僕は高校生でした。
今やアラフィフのおっさん。
平成の30年は、いろいろありましたが振り返ると後悔ばかり多かった気がします。
ああしておけばよかった、あの時こっちの道を選んでおけばよかった。
まさに平成の間にたまったものは、数えきれないリグレットの数々。
まぁ後悔を振り返ってもはじまらないし、アラフィフとはいっても人生まだまだこれからと、前向きに捉えたい。
令和の時代は、誰もが穏やかに豊かに暮らせる時代になることを願うばかりです。
さて、令和一発目の記念すべき記事は何を書こうかと思ったのですが、キン肉マンはあとまだ2週も待たなければいけない。
B’zのニューアルバムが発売されるのは5月末。
ゴジラも公開は5月末。
それではやっぱりゲームネタかな。
令和一発目のゲームネタ。
令和最初のゲームネタ。
令和、令和、れいわ、レイワ…
レイは⁉︎
というわけで「北斗の拳6」でレイを使用した苦行プレイを!
と、いうわけで令和最初の記事には令和のレイにあやかって「レイフォース」を選択した次第であります。
今回選択した「レイフォース」はiOS版。
タイトーのシューティングゲームレイ3部作の1作目になります。
と、偉そうに説明していますが「レイフォース」というタイトルにいまいちピンとこないワタクシ。
タイトーロックオンシューティングの第1作と言われたら、「レイヤーセクション」という名前がピンとくるんですね。
「レイヤーセクション」とは、セガサターン版の「レイフォース」。
諸事情あって、タイトルを変えての移植となったようですが、当時「レイフォース」という名前のゲーム会社が存在していたとのことで、その会社名と混同しないためのタイトル変更だったようです。
ですが、当時はそんな諸事情はよく知らず、ゲームセンターで「レイフォース」をそんなに遊ばないままに「レイヤーセクション」を購入した僕にとっては、このゲームは「レイヤーセクション」という名前の方がしっくり来るんですよ。
なので、このiOS版の「レイフォース」を遊んでいても、そのタイトルにちょっと違和感あったりします。
さて、その「レイヤーセクション」改め(いや改めているのはこっちの方ですが)「レイフォース」。
基本、オーソドックスな縦スクロールシューティングなのですが、特筆すべきはボムがないこと。
そのかわりにロックオンレーザーが搭載されており、最大8機の敵をターゲットロックオンし、一斉掃射する爽快感は一撃必殺のボムでは味わえないものでした。
そして、そのロックオンレーザーこそがレイシリーズを代表するものとなり、後の「レイストーム」「レイクライシス」にも引き継がれていったのです。
サターンソフトの「パンツァードラグーン」でもロックオンレーザーは存在しており、使用法としては同じものでしたが、3Dシューティングだった「パンツァードラグーン」に対して、「レイフォース」は2Dシューティング、また別の楽しさ、爽快感がありました。
出来るだけ多くの敵機を一度にロックオンしてレーザーで一掃すると、その分だけ高得点が得られるので、押し寄せる弾幕をくぐり抜けながらひたすらロックオンを目指したもんです。
この弾幕をかいくぐる2Dシューティングとしての一面が「パンツァードラグーン」との最大の違いでしたね。
そんな「レイフォース」、サターンで「レイヤーセクション」を遊んでから実に20年近くになりますか。
縦シューなんでiPhoneで遊ぶのもいいかとも思いましたが、弾幕を抜けるには少しでも大画面の方がいいだろうと思い、iPadの方で
遊ぶこととしました。
遊ぶこととしました。
タッチパネルで縦シュー、できるかな…
以前に「R-TYPE」や「メタルスラッグ」をスマホのタッチパネルで遊んだ時にはとても遊べるものではなかったのですけど。
「リミックスモード」なるものもあるようですが、とりあえずここは昔を懐かしんで「アーケードモード」で。
おっさんのふっとい指での「レイフォース」を令和元年にプレイ。
オープニングもしっかり再現されていて安心。
そうそう!こんなだった!
懐かしいなぁ「レイヤーセクション」。
いや、「レイフォース」か。
オープニングを堪能したあとでゲームスタート。
懐かしいけど、今更ながら令和の新時代に遊ぶゲームじゃないよなぁ。
それでも面白いものな面白いのですが…
やっぱり指では操作しにくいぃ!
ショットは当然のごとくオートにして勝手に連射されてます。
オプションで変更はできますが、タッチパネルで連打するとなると高橋名人だって無理ですって!
連射以前に指や自分の手で画面が隠れるし、弾幕が激しくなってきたら満足に弾を避けられません。
最初のボス戦から一生懸命。
スクリーンショットを撮るのも一苦労です。
しかし、ここで閃きました!
iPadなんだからApple Pencilを使ってみたらどうだろう?
早速Apple Pencilを手にしてプレイ再開。
指でのプレイとどう変わってくるでしょう?
なんということでしょう。
これが案外、指で操作するよりずっと良くって。
指で操作している時には引っかかるような感じもあったのですが、Apple Pencilだとスイスイ動いてくれます。
自分の指や腕で画面が隠れることもないので、弾幕を見極めながらApple Pencilで操作すればとても回避しやすい。
ロックオン操作も一通りロックオンしたあと、軽くペン先でタッチすればレーザー一斉掃射できます。
これは盲点だったなぁ。
Apple Pencilなんで、今持ってるiPhone6SやXperiaでのプレイは不可能ですが、他のタッチペンだとどうだろう?
それでも、ゲームパッドやスティックと比べると操作しにくいのは否めませんけどね。
後半になるにつれ弾幕も激しくなっていくので、Apple Pencilの操作でもストレスを感じることがしばしばありました。
でも、外付けのコントローラを用いないプレイでは指で操作するよりもずっと推奨できますApple Pencilでのプレイ。
難易度にも歯ごたえがあり、後半はゲームオーバーのオンパレードですが、それもシューティングゲームの醍醐味。
コンティニュー無制限でなかったら、ここまで遊べなかった…
グラフィックもいいですねぇ。
2Dドットグラフィックなのに立体感ありすぎる背景。
令和に遊ぶゲームじゃないなんて言ってスイマセン。
今でも十分通用するグラフィック。
20年近く前の平成初期のゲームだなんて思えません。
こんなゲームをサターンで遊べてたんだなぁ。
あと、BGMがすごくいいんですよ。
この「レイフォース」に限らず、「ダライアス」シリーズや「サイキックフォース」。
タイトーのサウンドチーム、ZUNTATAの創り出すBGMは常に神がかっていて、今聴いても鳥肌立ちながらのプレイができますねぇ。
Apple Pencilと無限コンティニューのおかげで最終ステージのラスボスまで来ましたよー。
サターンの「レイヤーセクション」を遊んでいた当時、僕や友人はこのラスボスのことをウォーカーギャリアと呼んでいました。
そして撃破ッ!
ラストのデモもしっかりと再現。
なんのグラかわからないようなスクリーンショットですが、敵の母星を星ごと破壊、消滅してしまいました。
ガミラスの都市を滅ぼした宇宙戦艦ヤマト(旧作バージョン)もビックリの結末ですが、そうそう、そんなエンディングでしたわ。

そしてエンディングへ。
令和の時代になって初めて遊んだゲームにして、エンディングを見たのは令和のレイにならって「レイフォース」となりました。
平成の時代にかつて遊んでエンディングまで見たんじゃないかって?
僕がかつて遊んでエンディングを見たのはセガサターンの「レイヤーセクション」であって、「レイフォース」というタイトルのゲームを遊んでエンディングを見たのはこれが初めてなんです!
せっかくなのでリミックスモードも遊んでみました。
グラフィックもBGMも特に変わっていないのですが、なにがリミックス?と思って説明を見てみれば、スマホなどのタッチ操作に最適化したモードだそうで。
確かにアーケードモードと比べるとスライド操作しやすくなったかな?
でも、出来ればやっぱりゲームパッドで遊びたくなるなぁ。
出来がいいだけに昔の感覚で遊びたくなっちゃいます。
SteelSeries Nimbus
この辺が良さそうなんですけどね。
「ファイナルファンタジーテクティクス」も眠らせたまんまだし、買ってしまおうかな…。
令和元年、レイにちなんだゲームはまだ「レイストーム」と「レイクライシス」が控えています。
令和元年中に記事に挙げてみようとは思いますけど、この僕のことだからどうなることやら。
まぁ令和のレイに因んでと言っても、「レイ・トレーサー」の記事は書きませんけどね!
PS2で「レイフォース」プレイするならコレらしい。
永遠の名作。


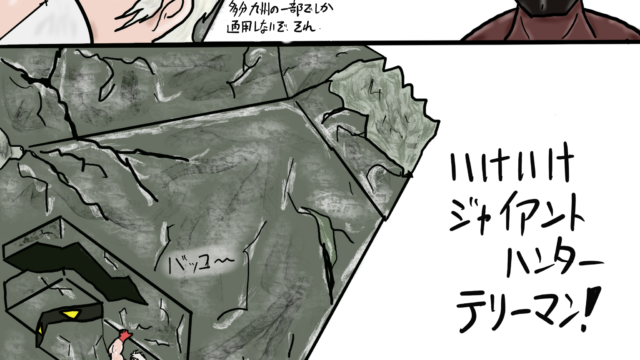
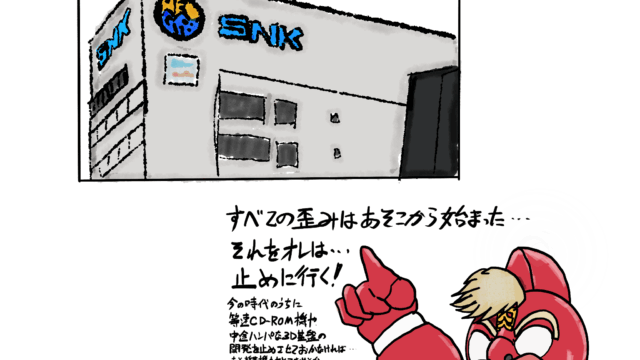




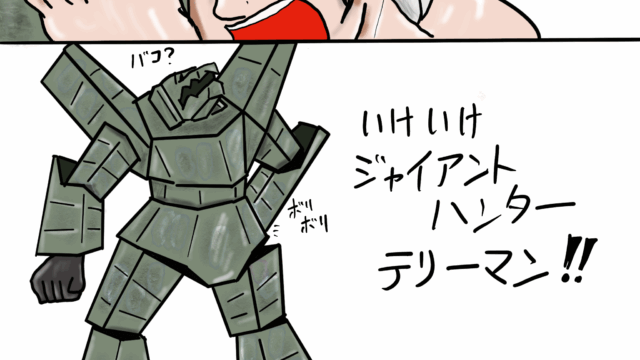



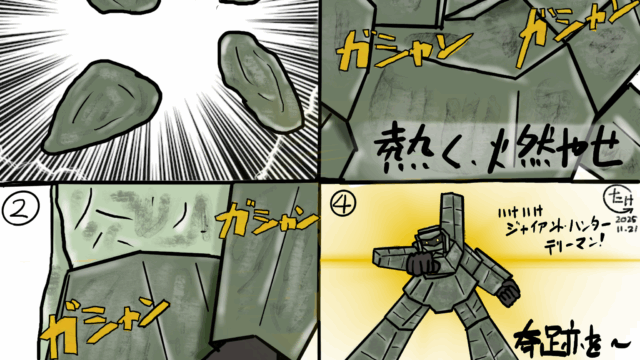
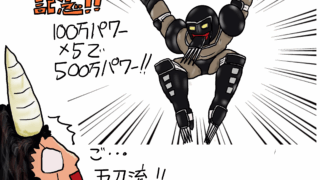


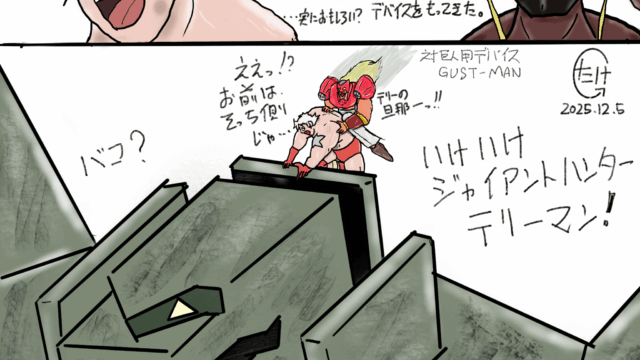

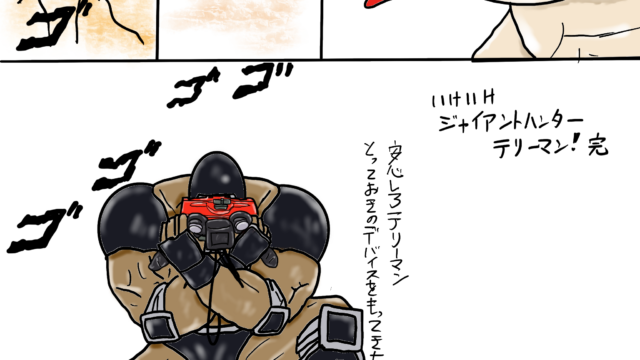

























コメント